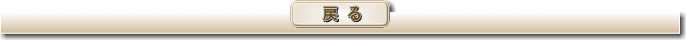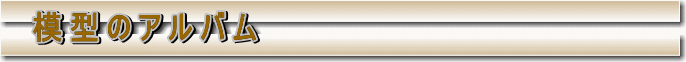
 |
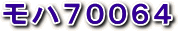
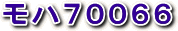
クハ76、サロ46と同時に購入したエンドウのモハ70です。 実物の基本編成は3M4Tで運転されていましたが、 この模型の編成ではモハ53がトレーラーとなっているので動力車はこの2両だけになります。 それでもこのモハはMPギヤーシステムによる全軸駆動ですので2M5Tでも充分な余力を持っています。
ACEカプラーの両脇にジャンパ線とジャンパ線受けを取り付けていた跡が見えます。
上回りはクハ76に準じて、元の塗装の上から青2号とクリーム2号を吹き付け、 屋根にもエコーのルーフィングサンドを撒いてキャンバス張りの表現をしています (このキャンバス張りが後で問題となるのですが・・・)。 パンタ廻りは、歩み板、避雷器、配線をマスキングテープでマスキングしてから ルーフィングサンドを撒きました。
落成当初は集電の安定性を考えて7両全車をジャンパ線で繋いでいましたが、 目の衰えとともにジャンパ線の接続が困難となってきたので、 集電ブラシをつけて全車輪から集電するようにしました。 トレーラーは絶縁側だけにブラシをつけましたが モハは車輪踏面の清掃も兼ねて全車輪にブラシを当ててみました。 その結果集電不良に陥ることは殆どなく快調に走るようになりました。 カプラーはドローバーをACEカプラーに交換しています。 ACEカプラーは旧型の軸距の長い台車と組み合わせると車輪と干渉するので、 車輪に当たる角の部分を少し削って取り付けました。
ナンバーはピノチオが以前に出した旧型電車の手引き(3)を参考に決めました。 ドア窓と戸袋窓がHゴム支持でDT20を履いているのは昭和29年製の040〜052か 昭和30年製の062〜074ですが、非パンタ側妻面に標識灯があるのは昭和30年製の062以降なので、 この2両は064と066にしました。ところが後によく調べなおしてみると 昭和30年製の053以降は屋根が金属製になっているではありませんか (053〜061は台車がDT17で標識灯もないので対象外)。 うかつにも金属屋根の70系は300番代だけだと思い込んでいましたが、 非パンタ側妻面に標識灯があり屋根がキャンバス張りのモハ70は実在しなかったのでした。 しかし一度撒いてしまったルーフィングサンドを剥すのは困難なので、 いずれ標識灯を埋めてナンバーを昭和29年製のものに変えてやらねば・・・
(2005年10月 S.N)
| 他の車輌の解説ページはこちらから | |||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |