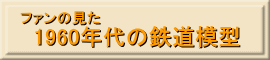 |
 |
 |
 |
 |
1-2 1960年代の鉄道模型の状況 (後編)
|
今回も先月に引続き1960年代の市販の鉄道模型製品をメーカー別にご案内します。
|
つぼみ堂模型店
|
トビー模型店
|
|
その他のメーカー −金属製製品− 宮沢模型からは1968年(昭和43年)にD50が発売されました。 市場に無い形式であったため期待されましたが、 基本的な設計は比較的良かったにも拘らずパーツの品質や組立てが悪く、 大いに損をした製品であったと思います。 珊瑚模型店は1969年(昭和44年)に2120を発売しました。 難しい古典機をうまく処理しスケール感も良く、 その後の珊瑚の蒸機バラキットシリーズの基礎となった製品でしたが、 この時は組立キットや完成品として発売されました。
ひかり模型はEF63のエッチング板を発売していましたが、 1966年(昭和41年)に特製品としてEF63の完成品を発売しました。 ピノチオ模型からは1960年代終盤に43系、 61系の客車が所謂真鍮バラキットのはしりとして発売され、 それまで良質の真鍮製製品の発売を待っていた旧型客車ファンに歓迎されました。 現在編成物を主に隆盛を誇っているエンドウは、 当時は遠藤商店(TER)の名で各種二軸貨車や1967年(昭和42年)にDD13、キハ02、 17系気動車を発売していたに過ぎませんでした。 −紙製製品−
京都のマツモト模型は多種のWルーフ旧型客車をペーパー製でバラキットと 塗装済完成車体を販売しており、戦前の旧型客車ファンには得がたい存在でした。 −9mmゲージ製品− 1966年(昭和41年)に関水金属が9mmゲージで初の製品として C50とオハ31を販売開始したことは鉄道模型界に新しい時代を告げるものでした。 基本的に運転が主体となるべきゲージの最初の製品として あえてこの古典的両形式を選んだ理由は今でも謎ですが、 その後103系、EF70、20系客車を発売、9mmゲージの基礎を築いていきました。 しかしながらHOの大きさに慣れてしまった目にはかなり小さく写ったことは事実です。 また結局市場には出回りませんでしたが、 あのソニーが9mmゲージのED75とスハ43の試作をしたこともありました。 |
まとめとして
当時の標準的な仕様としては、 車体は真鍮プレス加工のみというものが主流でエッチング併用はまだ少数派でした。 動力装置については、箱物は縦型モーターにウォーム+インサイドギヤーといったところで、 その後最も変化を遂げた部分かも知れません。 ロストワックスによる部品は主に輸出品を転用した部品が蒸機のごく一部に使われているに過ぎず、 挽物部品ないしはソフトメタル部品が多く使われていました。 プラスティック部品もまだ少なく、1960年代半ばから屋根上器具や床下器具に使われ始めた程度でした。 台車は主にドロップ製で立体感は乏しいものでしたが、 焼入れした鉄製のピボット軸の車輪の転がりは その後普及したダイカスト製台車の軸受けのものに比べ大変優れていました。 カプラーはベーカータイプが主で、カツミ、天賞堂、 カワイの編成ものはそれぞれ独自のドローバーを使用していましたが、 一部のファンはNMRA(X2F)型や天賞堂が輸入した高価なケーディーを使い始めていました。 製品の販売形態としては、 メーカーによって差はあったものの総じて言えば所謂バラキットはまだ少数派で、 組立済み未塗装または塗装済みキットと完成品の2つの形態が主流でした。 半田付けを必要とする部分が組立済みで、購入者は塗装をしたり、 窓ガラス貼りやライト類の取付け・配線、 動力装置を含む下廻りの組立を行う未塗装・塗装済みキットは現在ほとんどありませんが、 腕にそれほど自信のないモデラーがディテールの追加を気楽に行える点や、 車体や動力装置の構造を理解する一助になった点などは無視できない特徴だったと思います。 1960年代前半では完成品でも窓ガラスが入っていないものも多く、 天賞堂のDF50やED42でも未装着でした。 いずれにしても鉄道模型本来の「良く走る」ということが大事であり、 飾っておくだけの模型は無かったように思います。 当鉄道では当時より信越線の車輌を中心に集めてはいましたが、 前述のとおり製品化される機種・車種が限られていたため、 信越線の車輌以外でも品質の良い車輌や好みの型式は兄と小遣いを出し合い (と言っても年の差の分兄の方が多かったのは当然ですが)購入していました。 これらの車輌の一部は高校生の時代に手放してしまいましたが、 次回からは現在も当鉄道に在籍する1960年代の車輌を中心に、 メーカー別にご紹介していきたいと思います。やや車種やメーカーが偏ったものになりますが、 この時代の雰囲気を感じ取っていただければ幸いです。 ご参考までに1960年代に発売された主な製品を 年別、メーカー別に表にしてお目にかけます。 なお表の作成に当たっては機芸出版社発行のTMS各号を参考にさせていただきました。 (2007年8月 M.F) |
写真をクリックすると拡大画像が表示されます
 |
 |
 |
 |