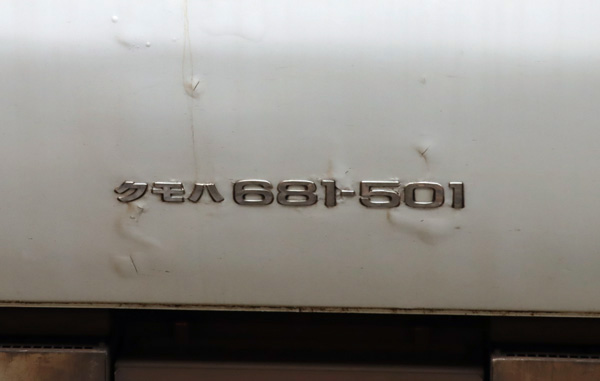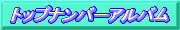 

|
 | |
名古屋駅で出発を待つ敦賀行き特急「しらさぎ」です。手前から、 クロ681-1(1号車)+サハ680-2+モハ681-1+サハ681-301+サハ680-1+クモハ681-501の、 6両編成です。 「しらさぎ」用は、客室窓下に青とオレンジのラインが入っています。 |
 | |
クロ681形の運転室部分。運転室窓が台形となっているのが、 量産車の特徴の一つで量産試作車の窓は三角形となっていました。 |
 | |
3号車は、モハ681-1です。1Mの電動車ですが、 集電装置はユニットを組むサハ680に搭載しています。 ユニットを組む相手は2号車のサハ680-2となります。 |
 | |
5号車サハ680-1です。付随車ですが、集電装置と変圧器、整流器を載せています。 ユニットを組む相手は、先頭車クモハ681-501となります。 |
 | |
敦賀側は、貫通型のクモハ681-501です。 |
 | |
何故か、貫通型運転台の扉には「業務用扉」と表記されています。 |
581系で登場した貫通形の特急車ですが、JR化後は各社それぞれ発展型に推移しましたね。 個人的にはJR西日本の681系が一番好みです。 今月の友情出演はそんなJR西日本の681系量産車をご覧ください。
(2025年7月 H・T)
今回のトップナンバーは、681系のクロ681-1、モハ681-1、サハ680-1 なのですが、 取上げた車両は、二代目となります。また、クハ681-1も在籍していましたが、 車椅子の設備対応化工事で200番台となっていますので、取り上げていません。
1987年(昭和62年)に国鉄が民営化されて、北陸を含む西日本地域はJR西日本として発足しました。 そのJR西日本、既に山陽道は山陽新幹線となっていましたが、在来線の特急として稼働していたのが、 京阪神と北陸を結ぶ特急「雷鳥」「スーパー雷鳥」でした。 しかし、並行する高速道路が整備され、 鉄道は所要時間短縮とより高いサービス提供が求められるようになり、 1992年(平成4年)に681系が試作されました。 当時、485系でも踏切のない湖西線や北陸トンネル内で130km/h運転が行われていましたが、 ブレーキ性能の向上を図り、踏切がある区間でも130km/h運転を目指しました。さらに、 将来は160km/h運転ができるような性能としています。そして、各種試験の後、 1992年末より「雷鳥」として営業運転に就きました。この結果を踏まえて、 1995年(平成7年)〜1997年(平成9年)に量産車が登場しました。 この時「スーパー雷鳥(サンダーバード)」の愛称が導入されています。なお、試作車は、 量産車と合わせるため、大改造されて、0番台から1000番台となりましたので、 量産車の形式番号は、あらためて「1」から付与されました。 この量産車が今回取上げたトップナンバーです。
車体は、普通鋼ですが、一部に高耐候性圧縮鋼材やステンレス鋼を採用しています。 また、試作車では、M車(VVVFインバータ制御機器)+Tp車(集電装置、変圧器、整流器) +T車(コンプレッサー、補助電電装置)と3両 1ユニット構成でしたが、 機器を小型化してM車+T車の2両 1ユニット構成になりました。編成も、 試作車は485系「雷鳥」に合わせて9両貫通編成でしたが、 七尾線への乗り入れを考慮し基本編成6両+付属編成3両となり 併結時は通り抜けができるように貫通型運転台車両が導入されています。 この貫通型前面形状は、以降登場するJR西日本の特急車両の顔に引き継がれています。
また、北陸本線では160km/h運転は実現しませんでしたが、 北越急行ほくほく線にて160km/hの営業運転を実現しました。
北陸新幹線が敦賀まで延伸され、「サンダーバード」「しらさぎ」の運転区間は、 大幅に縮小されました。681系は、余剰車が発生し廃車が始まりました。 トップナンバー編成も2025年(令和7年)1月に廃車となりました。
(2025年 T・O)