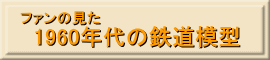 |
 |
 |
 |
 |
2. 模型店別車輌発売状況
2-2 カツミ模型店(2) −その他の機関車−
|
前回は一時代を画したシュパーブ・ラインの蒸機シリーズを取り上げましたので、
今回は1960年代にカツミが発売したその他の機関車ついてご紹介します。 1.蒸気機関車 これらの製品群のうち、7100型と150型はどちらかと言えば比較的初心者向けと考えられます。 C51とC58は他社の製品を改良して発売したようですが、C51は基本構成・スケールが比較的良好で、 車輪も全てスポークを使うなど当時の他社の製品と比べると魅力的で、 給水温め器の取付け等多くのファンのディテールアップの題材になったようです。 C58は宮沢模型の製品よりは実物の印象を捉えているようでしたが、 同年に発売されたシュパーブのD51を見た目には構造やディテールなど物足りなさは隠せません。 9700と9750は古典機としてはメジャーな形式でしたが、 やはりそのファン層は限られていたのではないかと思います。 その後、高価なシュパーブの蒸機シリーズとは一線を画す普及品として、 ディテール及び構造を簡略化し価格を抑えたダイヤモンドシリーズと銘打ったC62が1967年(昭和42年)に、 C59・C60が1968年(昭和43年)に発売されました。 残念ながらシュパーブ以外のこれらの蒸機群を筆者は購入しておりません。 理由は色々ありますが、当時古典機にはあまり興味がなく且つ欲しい形式でなかったことに加え、 やはりシュパーブの製品を見てしまった後はスケール感や構造・ディテールに満足がいかなかったためだと思います。 ここではノーブルジョーカーの中でSNが所蔵していた9750と HTが所蔵していたダイヤモンドシリーズのC59とC60並びに南薩タイプのCタンクをご紹介します。 |
9750
製品としては、古典機と言うこともあり、ディテールは少なくさっぱりしています。 真鍮プレス加工半田付け組立で、発売当時としてはシュパーブ以外の市販製品の水準をクリアしていました。 煙室扉はドロップ製でしたが、エッチングは使っておらず、ボイラーバンドは帯材の半田付けのようです。 ハイライトの2台の主台車は真鍮版の組立で、良く出来たダイキャスト製のスポーク輪心の動輪を履いています。 前部の台車はドロップ製の軸バネまで表現されていましたが、 残念ながら伝動は後部台車のみだったため前部台車の走行抵抗は大きく、 軸バネが入っていなかったこともあって大型機にしては牽引力がもう一つでした。 しかしマレー機の特色を生かし、うまく調整すれば450rのカーブを通過することが可能でした。 テンダー本体のリベットはプレスで表現し、縁は真鍮線を半田付けしていますが、 上部は何故か実物の一直線と異なり、後部が一段落ちた形状になっていました。 テンダー台車はドロップ製で車輪もスポークを履いています。 いずれにしても日本型のマレー機の発売は初めてで、その独特の走りっぷりはファンの注目を集めました。 |
C59・C60 (ダイヤモンドシリーズ)
販売価格:未塗装キット ― ¥5,490 シュパーブ製品としては最後の型式となったC55・C57が発売になった翌年、 カツミはダイヤモンドシリーズと銘打った普及版の蒸機シリーズの第1号としてC62を発売しました。 シュパーブシリーズに牽引させてバランスの取れる客車は、当時は天賞堂の軽量客車シリーズくらいしかなく、 またシュパーブはやはり高価であり普通のファンが何台も保有できる機関車ではなかったため、 廉価にしかし基本的なつくりをしっかりしたダイヤモンドシリーズの発売となったようです。 このシリーズは、手作業の半田付け組立を主体としたシュパーブとは大きく異なり、 全体としてはディテールを省略し、コストダウンのためダイキャストやプラスティックを多用していますが、 スケール感は良好で多くの方のディテールアップ工作の材料になりました。 特にC62の翌年に発売されたC59・C60は当時市場にカワイ製しかなく、ファンに歓迎されました。 上廻りはキャブ部・ランボードやドームがついたボイラー部・前部デッキ部・煙室扉部に分かれ、 煙室扉部が一体のダイキャストで作られている以外は真鍮版の加工によっており、ビスで組み立てます。 エッチングを使った部分はキャブのドアや窓枠などで、 ボイラーの帯や除煙板の縁取りはプレスで表現されています。 煙突はダイキャスト製ですが給水ポンプ・エアーコンプレッサー・動力逆転機・ キャブ天窓その他の小パーツは全てプラスティック製で、購入者が取り付けるようになっていました。 下廻りは主台枠・シリンダー部・従台車がそれぞれ一体のダイキャスト製で、 モーションプレートや先台車・ロッド類は真鍮プレス製です。 シリンダー部を一体ダイキャスト製にした例はカワイのC59にありましたが、 主台枠を一体のダイキャスト製にしたのはこの製品が初めてと思われ、 組立精度に気を使う必要もなく良い選択であったと思います。 何故かC62の従台車は形態の違うD62用のものを履いていたため、違和感がありましたが、 C59では主台枠後部を一体化した従台車がダイキャストで新規に製作され、 一体で空気分配弁も表現されており、キャブ下を引き締めていました。 全ての車輪と動輪の輪心はプラスティック製で、動輪のタイヤはメッキしたダイキャスト製です。 両側絶縁となるため、C62では動軸押え板に取付けた集電シューが両側の第2・3動輪のタイヤの裏側を擦っています。 C59では、集電シューがプラスティックのボックスに収められ第1・3動輪からの集電に改められました。 両側集電のためテンダーが無くても試運転が出来るのは便利でした。 軸バネは入っておらず、ブレーキシューは付いていません。モーターはどちらもDH13でした。 テンダーはダイキャスト一体で作られており、結構重量があります。台車も勿論ダイキャスト製です。 C62のテンダーは何故か一号機の後端が一直線のものでしたが、後のC59の発売が視野に入っていたのでしょうか。 ウェイトに鉛よりも比重の軽い金属が使われていたため機関車本体が軽く、また軸箱可動ではなかった一方、 テンダーがダイキャスト製で重く、牽引力はいまひとつでした。 しかしながら当時としては思い切った構成をとっており、 ディテールは少ないものの価格はシュパーブの半額程度であり、十分に存在価値のある製品でした。 写真のC60は多少ディールアップしてあるようです。 |
南薩5号タイプC型タンク
販売価格:組立済未塗装キット − ¥1,500 カツミがHOスケールの日本型に参入した1959年(昭和34年)、 自由型ではありますが南薩鉄道の汽車会社製Cタンク機をモチーフにしたC型タンクが発売されました。 それまで市場に出回っていた自由形のタンク機は基本的に入門者を意識して作られていたようですが、 このCタンクは動輪径が小さいものの実物の印象もある程度つかんでおり、 購入して改造のベースにされた方も居られると思います。 製品はプレスでボイラーバンドやリベット・窓枠を表現した真鍮版をプレス加工した後、 半田で組立てられています。煙室扉はドロップ製でよく出来ており、 所謂初心者向けのロコとは一線を画していました。 |
|
2.電気機関車 ED70
販売価格:組立済未塗装キット − ¥3,150 1950年代に一応国鉄のスケール機として市場で入手できたのは、 カワイのED14・EH10や鉄道模型社のED16・EF58などであり、 そのスケールや構造・ディテールなどにおいて未だ高級マニアを満足させられる製品ではありませんでした。 このような状況下で1960年(昭和35年)にカツミから発売されたED70は、 特にそのスケール感や印象把握において群を抜くものでした。 ED70はご存知のとおり北陸線の交流電化により登場した初の本格的交流電気機関車でしたが、 東京在住のものにとっては全く縁のない車輌でした。 しかしその出来の良さから多くのファンが購入したのがこの製品でした。 車体本体(側板と屋根)および妻板はプレスで成形したもので、 本体と妻板とは半田付けで組み立てられていました。窓枠のHゴムはプレスできれいに表現され、 正面窓にはただの真鍮線ではありましたが、ワイパーまでついていました。 屋根上の高圧線の碍子は形態のよい挽物を銀メッキしたものでしたが、 パンタの碍子とともに白色に塗装する必要がありました。パンタは当時の水準からすると形態も良く、 比較的すっきりと組み立てられていました。 側面のベンチレーターはエッチングで表現した真鍮板を側板裏側から貼り実感的に仕上っていますが、 写真の製品ではエッチングが外板の寸法とややずれているようです。 プレス製のスカートにはドロップで表現したジャンパー線受けを取り付け、 精密感を盛り上げています。キットは当時の他社製品と同様、 一個のモーターによりウォーム+インサイドギヤーで二軸を駆動する方式でしたが、 後に二個モーター仕様のキットも発売されました。 台車はシャープに表現されたドロップ製でスポーク車輪を履いていましたが、 ブレーキ関係の表現が省略されていたためやや物足りないものでした。 初期の製品では台車間の機器箱の囲いは実際の網で作られており、ファン心をくすぐるものでした。 タンク類は挽物です。 いずれにしてもスケールや印象把握において当時の電気機関車の水準を大きく引き上げたのがこのED70でした。 EF60 発売年:1964年(昭和39年) 販売価格: 塗装済キット − ¥6,200(一般塗装)¥6,400(特急塗装) 完成品 − ¥7,370(一般塗装)¥7,590(特急塗装)
車体はプレスでHゴム等を表現した比較的厚い真鍮板の半田付け組立で構成されており、 側面のベンチレーターはエッチングによりきれいに表現された板を側板裏に半田付けされています。 ED70にあったワイパーはありませんでしたが、 屋根上の手すりや避雷器、汽笛が取り付けられディテール豊かになっており、 乗務員扉の脇の窪みにある屋根に上る手すりも真鍮線で上手に表現されています。 全体の車体の印象は悪くありませんでしたが、正面から見ると前面の窓の上下寸法がスケールよりやや大きく、 またかなり艶のある塗装だったこともあり、多少オモチャ的な感じがしました。 パンタは特に質的向上は見られませんでした。 台車は黒メッキを施したドロップ製で枕バネ周辺やサンドボックス・ブレーキシュー等が別付けとなっているので、 立体感のある好ましい外観となっています。動輪の輪心は真鍮鋳物で実物同様の丸穴のあいたタイプを表現しており、 下廻りを精密感のあるものにしていました。 中間台車は脱線防止対策として小さいウェイトを取り付け、さらにコイルスプリングで前後の台車と結ばれており、 効果を上げているようでした。プレスで表現されたスカートにはドロップ製のジャンパー線受けが付き、 空気取り入れ口には網が貼られていました。モーターはDV18を初めから2台装備、 伝導は従来どおりウォーム+一部デルリンを使用して騒音の発生を抑えたインサイドギヤーでしたが、 300gもある大型のウェイトと相まって強力機となり、長大編成を牽き運転会の華として大いに活躍しました。 この製品は天賞堂やシュパーブのような高級製品を狙ったものではなく、 初級者が多少手荒く扱ってもびくともせず、 適度なディテールを持ちガンガン走らせて楽しむモデルとしての存在感がありました。 EF70
販売価格: 塗装済キット − ¥6,500 完成品 − ¥7,700 上記のEF60とほぼ同時に、北陸線で初の交流F型機である客貨両用機として活躍していたEF70が発売されました。 製品のレベルや構成は当然EF60と同様ですが、交流機として、屋根上の高圧線用の配線や機器が目立つロコです。 その高圧線用の碍子は、ED70同様形態は好ましい物でしたが、完成品でも銀メッキのままで塗装はされていません。 側面のベンチレーターはEF60と異なり、直接側板にエッチングで表現されています。 床下には空気タンクも表現されていました。 このモデルには実物どおりのローズ系に塗装した製品と、朱色系に塗装した製品がありました。 朱色系のものはデパート等向けに販売したようですが、筆者も実物の交流専用機を見たことがなく、 暫くはこの朱色が実機の色と思っていました。 (2007年10月 M.F) |
写真をクリックすると拡大画像が表示されます
 |
 |
 |
 |